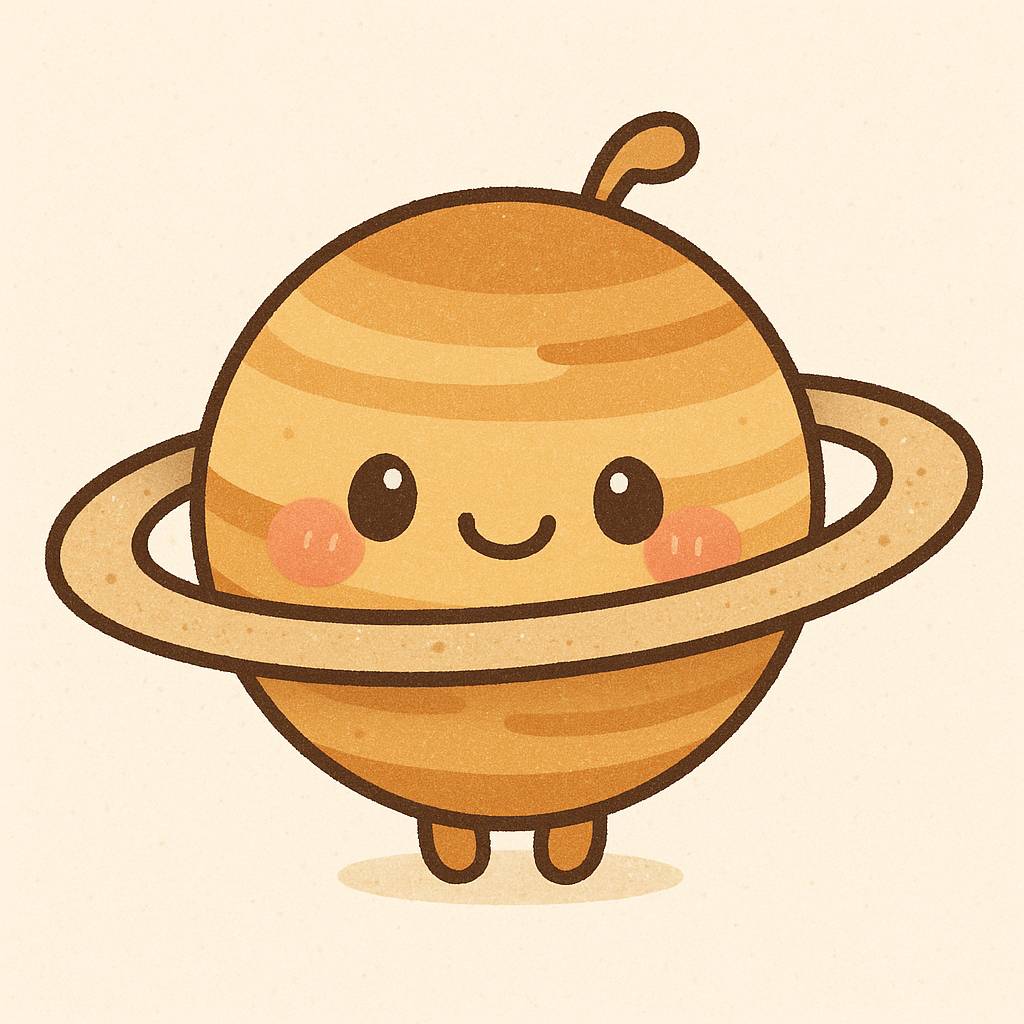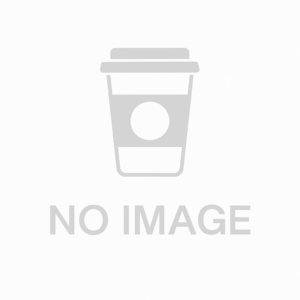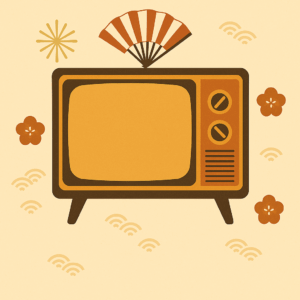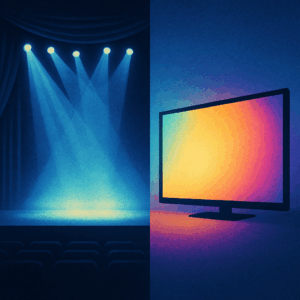「本物の外科医さん」は、現役の心臓外科医・北原大翔(きたはらひろと)さんが運営する人気YouTubeチャンネルです。慶應義塾大学医学部を卒業後、2016年に渡米して米国・シカゴ大学で心臓外科医として勤務。国内外での豊富な経験をもとに、医療のリアルやキャリアの裏側をわかりやすく発信しています。医師としての活動に加え、NPO「チームWADA」を通じた若手支援、講演・書籍など多彩な発信でも注目を集めています。妻の「うたさん」との結婚や猫との日常もファンに人気です。
プロフィール・経歴・活動(本物の外科医は何者?/北原大翔 経歴/イベント/本)
「本物の外科医さん」は、心臓外科医・北原大翔(きたはら ひろと)さんが運営するYouTubeチャンネルです。現役の外科医としての視点から、手術室の実際、チーム医療、キャリア形成などを一般の視聴者にも分かりやすく発信しているのが特徴で、「本物の外科医 何者?」という検索が増えるほど注目を集めています。
プロフィールとしては、日本の医学部を卒業後に臨床・研修を経て海外(米国)で心臓外科に携わる経歴が広く知られており、医療現場の透明性を高める姿勢が支持の理由です。
経歴面では、国内の基礎・初期臨床を経たのちに渡米し、英語環境での診療・教育・研究に携わってきたことがトピックです。動画や講演では、外科医の1日、キャリア選択、海外で働くための手順など“実務に役立つ話”が多く、医学生や若手医師からの支持も厚いです。
活動領域はYouTubeにとどまらず、オンライン/オフラインのイベント登壇、医療系メディアでのインタビュー、留学や海外就労を目指す医療者への情報発信など多岐にわたります。
著作(本)では、海外医療キャリアや働き方をテーマにした内容が知られ、実体験ベースの知見がまとめられています。読後に行動へ移せる“現場の知恵”が好評で、チャンネルの人気動画と相互に送客し合う導線になっています。YouTubeの再生リスト/人気動画(オペや心臓外科の基礎、キャリアQ&A など)から入って、講演や書籍で深掘りする読者・視聴者が多いのも特徴です。
家族・妻・子供・ペットの猫(結婚/北原大翔 妻/うたさん)
家族については、公に「結婚」を発表しており、「北原大翔 妻」「うたさん」という検索が多く見られます。YouTubeでは結婚報告の動画が公開され、妻は通称「うたさん」として登場することがあり、記事やインタビューでも結婚に触れられることがあります。
プライバシー保護の観点から、妻の職業や詳細な経歴、子供に関する具体情報は大きくは明かしていないものの、生活の一部や価値観を共有するスタイルが好感を集めています。
なれ初めに関しては、結婚式のオープニングムービーで公開しているほか、婚活や結婚観をテーマにしたコンテンツもあり、本人の言葉で「結婚に至る考え方」や「価値観の共有」が語られてきました。
「夫婦で支え合いながら、忙しい臨床と発信活動を両立している」という姿が伝わります。
また、ペットの猫「しんぞー」を飼っていることでも知られます。動画やSNSでは猫との日常が紹介されることもあり、医療の硬派な話題の合間に“人となり”が伝わるエピソードとして人気です。
こうした家庭的な一面が、視聴者の親近感を高め、ファン層の広がりに寄与しています。
英語・年収(英語発信/北原大翔 年収)
英語については、海外の医療現場で働くうえで欠かせないコミュニケーション力をベースに、英語環境での診療・教育・研究に携わっている点が大きな特徴です。
動画やインタビューでは、日本と米国の医療制度・文化の違い、チームの役割分担、患者や同僚とのコミュニケーションなどを具体的に語り、これがキャリアとしての強みになっています。留学・海外就労を目指す医療者にとって、学習の道筋やマインドセットが実例とともに示されているのが評価されています。
年収については、個人の具体額は非公開です。「北原大翔 年収」という検索は多いものの、公に確定できる一次情報は提示されていません。一般論として、米国の医師は専門領域・勤務形態・地域・経験年数などでレンジが大きく異なります。
日本と海外では医者の給与形態に大きく差があり、優秀な医者が海外に流出してしまう要因となっています。
5000万を超える年収を得る人もざらにいるといい、生活費も高くかかる環境とはいえかなり高収入な職業といえます。
「臨床(心臓外科)を軸に、YouTubeや講演、執筆・監修など多面的に活動している」という感じですね。
視聴者にとっては、年収の金額そのものよりも、英語力・臨床スキル・発信力を掛け算した“キャリアの再現性”こそが重要なポイントだと言えるでしょう。
総じて、北原大翔さんは「本物の外科医」としての実務と、わかりやすい発信を両立する稀有な存在です。プロフィールや経歴の強さに加え、家族や猫を含む日常の発信、英語環境での臨床経験、イベント・著作といったアウトプットの積み重ねが、専門外の読者にも届く“開かれた医療”を実現しています。